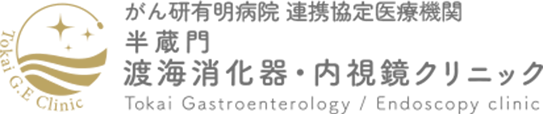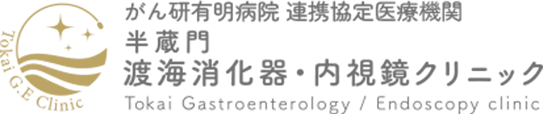大腸がんリスクと予防法の知識
2025/01/07
大腸がんは、日本を含む多くの国で主要な健康問題となっています。厚生労働省が公開した「令和2年全国がん登録罹患数・率報告」によると、大腸がんは2020年の部位別がん罹患数では男女ともに2位で、部位別がん死亡数では女性で1位、男性では2位と報告されています。
近年の調査によると、生活習慣の変化や食事内容が大腸がんのリスクに大きく影響を与えることが明らかとなっています。この記事では、大腸がんに関するリスク要因や、どのような方法で予防できるのかについて詳しく解説します。特に内視鏡検査の重要性や、早期発見による治療の可能性についても触れていきます。大腸がんのリスクを理解し、適切な予防策を講じることは、私たち自身の健康を守るために欠かせません。正しい知識を身につけ、実践することで、健康な生活を送る手助けができれば幸いです。
目次
大腸がんのリスク
大腸がんのリスク要因としては、肥満、運動不足、脂肪や肉類・加工食品の多量摂取、長期にわたる喫煙や飲酒があげられます。このため、生活習慣を見直すことが予防につながると言われています。日常生活において、自己管理を行い、健康的な食生活と運動を心がけることで、大腸がんのリスクを大幅に減少させることができます。以下リスクについて詳細にご紹介します。
食生活もたらすリスク:私たちの食事が大腸がんに関与する
大腸がんのリスクとなる食事は、脂肪や肉類の高摂取や加工食品、アルコールの多量摂取、食物繊維の摂取量が少ない、など食事内容が大きく影響しています。
<脂肪や肉類の高摂取>
脂肪のなかでも特に動物性脂肪、そして赤肉(牛・豚・羊などの肉)の高摂取が大腸がんのリスクを高めると考えられています。しかし、それは摂取量の多い海外での話で、日本人では事情が少し異なります。
2007年には米国がん研究協会(AICR)と世界がん研究基金(WCRF)により、赤肉、加工肉の摂取が大腸がんのリスクを上げることが「確実」と判定されています。そのなかで、赤肉は調理後の重量で週500グラム以内、加工肉はできるだけ控えるように、と勧告されています。
一方、2011年に発表された日本での研究では、女性では毎日赤肉を80グラム以上食べるグループで結腸がんのリスクが高い。という結果が出ましたが、男性では赤肉では特に関連はみられていません。また、加工肉については男女ともに関連はみられていません。なぜ日本と世界で乖離があるかというと、2013年の国民健康・栄養調査によると日本人の赤肉・加工肉の摂取量は一日あたり63グラム(うち、赤肉は50グラム、加工肉は13グラム)で、世界的に見て摂取量が低い現状があります。
大腸がんの発生に関して、日本人の平均的な摂取の範囲であれば赤肉や加工肉がリスクに与える影響は無いか、あっても、小さいと言えるでしょう。また、赤肉はたんぱく質や鉄、亜鉛、ビタミンB等健康維持にとって必要な成分も多く含んでいます。飽和脂肪酸も含まれるため、少なすぎると脳血性のリスクが高くなることがわかっています。そのため、極端に量を制限する必要性はないでしょう。
<アルコールと大腸がん>
男性では、飲酒しない人に比べて、アルコールを日本酒換算で1日平均1合以上2合未満摂取する人は大腸がんの発生率が1.4倍、1日平均2合以上摂取する人は、2.1倍でした。女性では、週1日以上飲酒する人でも、飲酒しない人に比べて、発生率は上昇しませんでした。これは、1日平均1合以上飲酒する人がほとんどいないためで、大量飲酒すれば男性の結果と同様である可能性があります。
アルコールが大腸がんのリスクとなる原因としては、アセトアルデヒドがあげられます。アセトアルデヒドはお酒に含まれているエタノールは分解されることで生成され、これががんの発生にかかわると考えられます。お酒を飲むと顔が赤くなる、気分が悪くなる、頭痛がする、などの原因物質です。大腸がん以外でも食道がんのリスクとされます。
<食物繊維と野菜・果物の摂取>
食物繊維は大腸がんのリスクを減少させるとされています。食物繊維は胆汁酸と結合して,一次胆汁酸から発がん促進作用のある二次胆汁酸への変換の阻止や、腸内の嫌気性菌の繁殖の抑制、さらに便量を増加させることで便の大腸通過時間を短縮させることで便内の発がん物質を希釈させることにより,大腸がんの発生を予防するとされます。
生活習慣がもたらすリスク:私たちの生活習慣が大腸がんに関与する
大腸がんのリスクには、食事以外にも運動不足、肥満、長期にわたる喫煙など、生活習慣が大きく影響しています。
<たばこと大腸がん>
男性でも女性でも、たばこを吸う人は、吸わない人に比べて、大腸がんの発生率が1.4倍でした。たばこをやめた人も、1.3倍でした。
たばこの煙には多くの発がん性物質が多く含まれており、喫煙によりたばこの煙が触れる気管、肺以外にも、直接触れない大腸の粘膜からも発がん性物質が検出されます。これによってがんが発生しやすくなるとされます。
<運動不足・肥満と大腸がん>
運動不足などにより身体活動が活発でないと腸管の動きが悪くなり便の通過時間が長くなり、その結果、発がん物質にさらされる時間が増して、大腸がんのリスクが高くなると考えられています。
また、肥満に関しては、男性において、BMIが27以上が確実なリスク上昇因子とされています。
大腸がんの検出法
上述のような大腸がんのリスクに加え、家族歴や遺伝的要因も無視できません。食生活・生活習慣に気を付けていても、大腸がんが発生することがあり、大腸がんの早期発見には内視鏡検査が欠かせません。40歳を過ぎたら定期的に検査を受けることが推奨されており、症状の出づらいポリープや初期段階のがんを発見することが可能です。早期発見により早期に内視鏡などで治療が行えるため、死亡リスクを大幅に下げることができます。
内視鏡検査の重要性:早期発見が運命を変える
健診で行われている便潜血検査では、初期の大腸がんやポリープを検出するのは難しく、進行がんになって発見されるケースがほとんどです。痔核などにより便潜血陽性となって大腸内視鏡検査を受けたところ、初期の段階で発見されることはよくありますが、内視鏡検査を受けないと初期の段階で診断を行うことは非常に難しいと考えられます。
内視鏡検査を受けることで、粘膜の変化やポリープを早期に発見することができ、これにより、がんの進行を防ぐ可能性が高まります。日本では、50歳以上の人を対象に定期的な検査が推奨されており、特に家族に大腸がんの既往歴がある方は、早めの検査を受けることが重要です。
文責:半蔵門 渡海消化器・内視鏡クリニック(東京) 渡海 義隆